とうもろこしの栄養と効果(まとめ)

とうもろこしの栄養と効果についてお伝えしていきます。夏野菜の代表格といえば「とうもろこし」。
茹でてよし、焼いてよし、スープにしてもよしの万能野菜ですね。とうもろこしの旬は6~9月ですが、なかでも7、8月の真夏がもっとも糖度が高い時期でしょう。とうもろこしは摂れたてが一番甘みがありジューシーですが、収穫してから時間が経つにつれて甘みが弱くなります。
とうもろこしは一般的な種類の他、ポップコーン専用の爆裂種や、若採りしたヤングコーンなど、品種改良されたものを含むと多くの種類があります。
今回のテーマはそんなとうもろこしについてです。グルメな食材、とうもろこしの栄養と効果についてじっくりと見ていきましょう!
目次
とうもろこしの栄養と効果 一覧
食物繊維 - 腸内環境を改善し、血糖値上昇を抑える

とうもろこしの栄養で豊富なのが食物繊維。
とうもろこしは不溶性食物繊維が多い食品。とくに実(粒)の皮にセルロースと呼ばれる食物繊維が含まれています。
食物繊維は腸内環境を整え、腸の動きも活発にしてくれるので、便秘の解消や大腸がんの予防に効果があります。そして、便秘は肌荒れの原因でもあるので美肌づくりにも有効な栄養です。
また血中コレステロールや血糖値の上昇を抑える働きがあり、高血圧や肥満、糖尿病の予防に効果があるとされています。
茹でても失われにくいビタミンB1 - 疲労回復効果に期待の栄養!
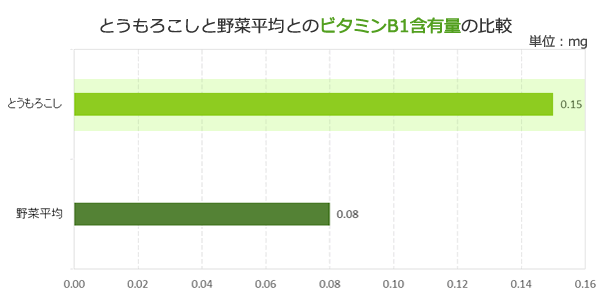
「日本食品標準成分表2015」より (可食部100gあたり、野菜平均は良好倶楽部調査)
とうもろこしに含まれている栄養のひとつビタミンB1は、野菜平均の約2倍と、野菜の中でも比較的多く含まれています。
効果や働きとしては、ビタミンB1は全身にエネルギーを行き渡らせる働きがあります。糖分をエネルギーに変えるのに大切な栄養で、不足するとイライラしてしまったり、注意力が低下するなど脳にも影響します。
また、ビタミンB1はアルコールの代謝にも関わるほか、疲労回復効果もあり、肩こりや手足のしびれなどを予防する効果も期待できます。
ビタミンB1は水溶性のビタミンですが、でんぷん層に包まれているため、茹でても失われにくい性質があると言われています。
ビタミンB1は、豚肉やうなぎ、玄米などにも含まれています。とくに豚肉に豊富なのでとうもろこしと一緒に、お酒のおつまみにするのもいいですね。
発育や美肌に効果的な栄養 - ナイアシン、ビタミンB2
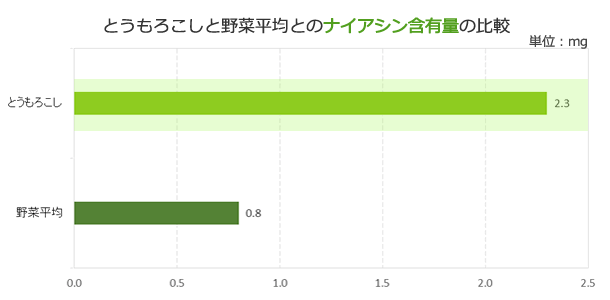
「日本食品標準成分表2015」より (可食部100gあたり、野菜平均は良好倶楽部調査)
とうもろこしに含まれるナイアシンは、野菜平均の2.8倍と豊富です。
ビタミンB2やナイアシンの効果や効能には、エネルギーの代謝を促進させる作用があり、ダイエット中の方にはとくに摂りたい栄養です。
さらにこれら栄養には、皮膚や粘膜の再生を促す働きもあり、健康を維持するために必要な成分です。口内炎や皮膚の炎症、目の充血を改善させる効果があります。
ビタミンB2やナイアシンもビタミンB1同様、水溶性でありますが茹でても失われにくくなっています。
強い抗酸化作用のビタミンE - 血行を促進、美容効果
とうもろこしに含まれる栄養素ビタミンEは、ビタミンの中でも強い抗酸化作用があるのが特徴です。
血行を促し、冷え症や肩こりに効果的です。またシミやしわを防いで、肌のハリを整えてくれるなど、さまざまな美容効果があります。
また、おなじく抗酸化作用をもつカロテノイドの一種「ゼアキサンチン」も含むため、より高いアンチエイジング効果が期待できます。
ビタミン類はとうもろこしの発芽部分に多く含まれているので、粒を手で取って食べるとより効果的です。
カリウムも豊富に含まれる! - 生活習慣病の予防する栄養
カリウムを豊富に含むとうもろこし。
カリウムはナトリウムを排出して血圧の上昇を防ぐ働きがあり、高血圧予防に効果がある栄養です。また利尿作用もあり、老廃物を体外に排出してくれます。
さらに筋肉の働きを活発にしてくれるので、健康維持にも期待できます。
茹でたとうもろこしや焼きとうもろこしには、塩や醤油を塗って食べる機会が多いので、とうもろこしのカリウム効果が効きますね。
とうもろこしのひげにも効果が!? - 利尿作用や抗酸化作用をもつ栄養も

とうもろこしのひげ茶が健康食品として売られていますが、ひげの部分にはカリウム、ブドウ糖やクエン酸、ビタミンKなどの栄養が含まれています。
とうもろこしのひげを煎じて飲むと利尿作用で、カラダのむくみの解消、膀胱炎や尿道炎にも効果があるといわれています。
服薬中の方はひげ茶と一緒に飲めない薬があるので、ご注意ください。また血中のカリウムを減らす作用があるので、授乳中の方もお控えください。
また、とうもろこしのお茶には、とうもろこしの実(粒)を煎った「とうもろこし茶」、ひげを利用した「とうもろこしのひげ茶」があります。とうもろこしのひげは南蛮毛(なんばんもう)と呼ばれ生薬にも利用されています。
| エネルギー | 水分 | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食物繊維 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92kcal | 77.1g | 3.6g | 1.7g | 16.8g | 3.0g | Tr |
| カリウム | カルシウム | マグネシウム | リン | 鉄 | 亜鉛 | 銅 |
| 290mg | 3mg | 37mg | 100mg | 0.8mg | 1.0mg | 0.10mg |
| マンガン | ビタミンA | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ビタミンB1 | ビタミンB2 |
| 0.32mg | 4μg | 0μg | 0.3mg | 1μg | 0.15mg | 0.10mg |
| ナイアシン | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | ビオチン | ビタミンC |
| 2.3mg | 0.14mg | 0μg | 95μg | 0.58mg | 5.4μg | 8mg |
とうもろこし(生)の100gあたりの成分表(Tr:微量「日本食品標準成分表2015年版(七訂)」より)
とうもろこしのおいしい茹で方!ふっくらジューシーに
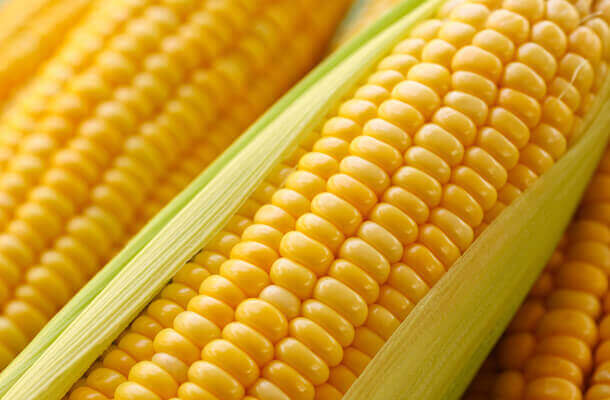
とうもろこしをふっくらジューシーに茹でるには、薄皮を残した状態で茹るのがコツ。
とうもろこしの皮をすべて剥いてから茹でると、茹でたてはふっくらとしていておいしいですが、冷めるととうもろこしにしわができ、味が落ちます。
おいしい茹で方は、とうもろこしの薄皮を残して皮を剥き、水から茹で、沸騰してから5分間茹でるだけ。
ふっくらジューシーなうえに、糖度までもがアップします。ぜひ、お試しあれ!
引用および参考:「日本食品標準成分表2015年版(七訂)」
関連コンテンツ
関連記事
"とうもろこし"の関連情報
- とうもろこしの栄養と効果(まとめ)
- とうもろこしのカロリーを徹底検証
- とうもろこしの旬はいつ?









