パイナップルの栄養と効果5選

ジューシーでさわやかな酸味と甘みが魅力のパイナップル。
南国フルーツの代表格でもあるパイナップルは、ゴツゴツとした厳つい形からは想像もつかないほどの、果汁の多さに驚かされます。
パイナップルはデザートや、酢豚やバーガーなどで美味しく味わうだけでなく、暑い夏を健康に過ごすために必要な栄養が豊富です。
今回はそんなパイナップルの栄養や成分とその効果についてご紹介します。
目次
パイナップルが含む栄養と効果 一覧
注目の成分!ブロメライン - 胃腸を健康に保つ効果、消化促進作用
パイナップルには、ブロメラインが豊富に含まれています。タンパク質を分解する酵素の一種で、キウイや梨などにも含まれています。
ブロメラインは、胃液の分泌を活発にして肉や魚などの消化を促進します。そして、胃もたれを防いで胃や腸を健康に保つ働きがあります。
消化に加えお肉も柔らかくするので、酢豚やハンバーグなどのお肉料理にパイナップルが入っているのは、理にかなった調理法なんですね。
リンゴ酸やクエン酸の働き - 疲労回復や夏バテ予防に
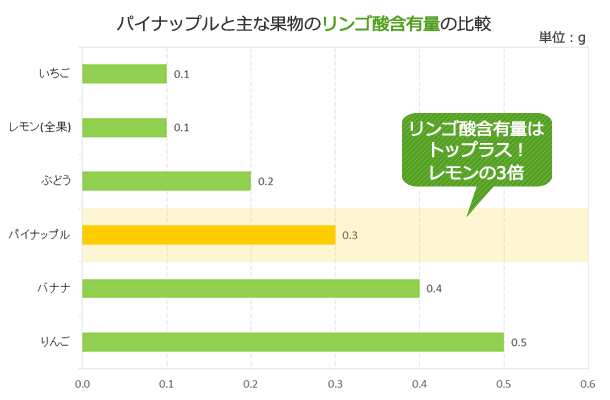
「日本食品標準成分表2020」より (可食部100gあたり)
パイナップルには、リンゴ酸やクエン酸といった有機酸が含まれています。
パイナップルに含まれるリンゴ酸やクエン酸の含有量は、全食品の中でもトップクラスを誇ります。また、リンゴ酸についてはりんごやバナナには劣りますが、レモンの3倍もの量を含んでいます。
クエン酸やリンゴ酸は、TCAサイクルの合成を円滑にする働きがあり、エネルギーの生成を促がすことで疲労回復に優れています。
またパイナップルの栄養にはエネルギー源の糖質や、その糖質を素早くエネルギーに変えるビタミンB1も含むため、夏バテの予防にも効果があります。
マンガンも含まれる - 骨や関節を丈夫に、骨粗しょう症を予防
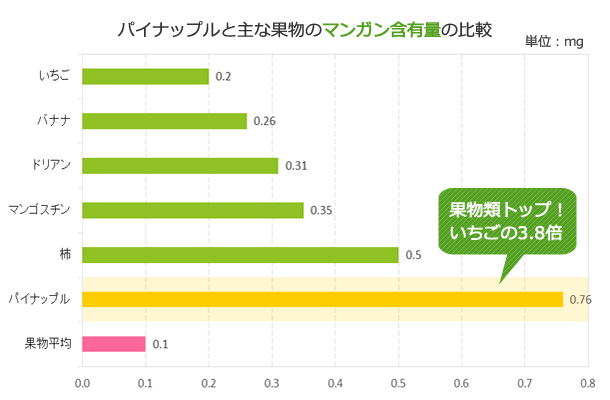
「日本食品標準成分表2020」より (可食部100gあたり)
パイナップルは、マンガンの含有量にも注目です。
パイナップルのマンガンの含有量は全食品の中では少ないですが、生の果物類と比較するとトップとなります。割と多めに含まれているマンゴスチンや、ドリアンと比較しても2倍以上の量を含み、いちごに至っては3.8倍にもなります。
成人の一日のマンガン摂取量は、「男性:4.0mg」「女性:3.5gm」です。通常の食生活では、過不足の心配はないと言われています。
マンガンはカルシウムやリン、銅とともに骨の形成に関わるミネラルです。骨の石灰化を促して骨や関節を丈夫する栄養で、骨粗鬆の予防になります。
食物繊維とブロメラインの効果 - 便秘の改善効果、整腸作用
パイナップルには食物繊維も含まれています。
食物繊維は第6の栄養素とも呼ばれる栄養で、腸の動きを活発にして便通を促し、腸内環境を整えて便秘を改善する効果があります。
また、ブロメラインにも整腸作用があり、下痢や腹部膨張感(ガスたまり)、便の悪臭などを改善する効果があります。
ビタミンCやビタミンB群の働き - 夏場の肌トラブルを予防
パイナップルには、上記のクエン酸やリンゴ酸などの栄養以外にも、暑い夏を過ごすために必要なビタミンやミネラなどの栄養が数多く含まれています。
夏は紫外線が強く日焼け止めも塗るので、肌のトラブルがつきものです。紫外線からシミやしわを防ぐ栄養にはビタミンC、皮膚や髪、爪を丈夫にする栄養はビタミンB2の働きです。また、ビタミンB6は肌荒れを防ぎ美肌を保つのに必要な栄養となります。
パイナップルはカリウムも含んでいます。摂りすぎたナトリウムや余分な水分を排出し、むくみの改善に有効となる栄養です。
| エネルギー | 水分 | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食物繊維 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54kcal | 85.2g | 0.6g | 0.1g | 13.7g | 1.2g | Tr |
| カリウム | カルシウム | マグネシウム | リン | 鉄 | 亜鉛 | 銅 |
| 150mg | 11mg | 14mg | 9mg | 0.2mg | 0.1mg | 0.11mg |
| マンガン | ビタミンA | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ビタミンB1 | ビタミンB2 |
| 1.33mg | 3μg | 0μg | Tr | 1μg | 0.09mg | 0.02mg |
| ナイアシン | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | ビオチン | ビタミンC |
| 0.2mg | 0.10mg | 0μg | 12μg | 0.23mg | 0.2μg | 35mg |
パイナップル(生)の100gあたりの成分表(Tr:微量、-:未測定「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」より)
間食にはドライフルーツのパイナップルを!

パイナップルは、ドライフルーツにも加工されています。水分が抜けて手軽に食べられるので、間食におすすめです。
含まれる栄養は乾燥状態にもよりますが、一日に不足しがちな食物繊維を補うことができます。食物繊維でお腹が膨らみ、ほどよい甘酸っぱさが満足感を与えてくます。
ヨーグルトに加えれば乳酸菌やカルシウムなどの栄養も摂れ、よりお通じも快適になります。
ただ、栄養が摂れる反面、糖分も多いので他の食品と上手に組み合わせて摂りましょう。ドライのパイナップルは「30g:104カロリー」ほどになります。
引用および参考:「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」
関連コンテンツ
関連記事
"パイナップル"の関連情報
- パイナップルの栄養と効果5選
- パイナップルのカロリー比較
- パイナップルの旬はいつ?






